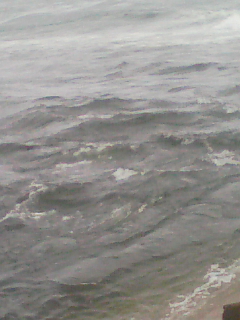日々録
日記のようなものを書いてみようかな、と思いまし
た。
備忘録を兼ねて、日々思ったことを書き付けておこうか、とい
う事です。
独り言めいた内容もありますが、興味があれば、お読み下さ い。 |
【17年8月31日】
俳句のお仕事、先ほど終了。
原稿をプリントアウトして、郵送する。
一応書き上げてのち、3日間毎日読み直しては、表現の確認や句読点まで含めての推敲作業。
時間を置きつつ繰り返し読み直すことで、見落としの部分とか、表現の曖昧な部分などに手をいれることができた。
ここまでかな、との判断で、8月最終日に投函。これで、一仕事終える。
純粋に俳句関係の仕事をこなすことはめったにないことなので、一層慎重にもなったものだ。
投函し終えて、ひとつ解放された気分になる。
昼食後、昼寝。
食べてすぐ横になると牛になったり、逆流性食道炎になったりして良くないとはいうけれど、本日は大目にみる。
涼しい風が窓から吹き込んできて、数分眠ったようだった。
気分爽快となって起きる。
明日から9月に入る。
内輪だけの集まりではあるが、講演会のその準備に入らなければならない。
岩城先生をテーマとする講演。
手元にある資料をもう一度読み直さなければならない。
頭の中では、展開を組み立て始めてはいるのだが、実際のところどうなるかは、いまのところ混沌。
北朝鮮のミサイルは、日本にとっては、あらたな「黒船」の襲来であるのかもしれない。
「たった2杯で夜も眠れず」と揶揄した狂歌があるけれど、そんな庶民の無知なたくましさを思う。
確率的にいって、自分の頭上にそれが落ちてくる可能性は、ほぼゼロであろうけれど、それでも1本のミサイルで、てんやわんやしている国民というのはどうなのだろうか。
そのように漠然とした恐怖感が国民の間に広がっているのは、政府の無策(それどころか、進んで恐怖を煽っているような気配すらあるけれど)の反映なのかもしれない。
それはともかく、この問題が武力による解決に結びつかないように、今こそ政治家の力量と手腕に切に期待するほかない。
それにしても、総理は米国とこの問題に関する認識は100パーセント一致すると繰り返し強調しているけれど、すべての可能性を机上においた米国との対策上の完全シンクロ状態ということは、武力による解決というプランも、当然その中に含まれているということを意味するのだろうか。
「Jアラート」は平成の「空襲警報」といった人がいたけれど、まさにそのようなものであるということか。
核シェルターの人気があるらしい。
資産に余裕のある人は、個人仕様のシェルターを、居宅の地下にどっしりと据えて、来るべき核戦争のために準備するのであろうか。
ただ、それが実際使われる状況になったとき、世界は果たしてどうなっていることだろうか、とちょっと気懸かりに思う。
SF小説的展開でいえば、生き延びたことがさらに悲惨な状況をその身にもたらす、などということもあり得るかもしれない。
核シェルターが、ちょっとおしゃれで贅沢で物珍しい応接室やミニシアターとか物置などとして使用されることを願うばかり。
【17年8月27日】
昨日、今日と暑さがおさまっているようだ。
最高気温も30度くらいで、大陸からの気団が降りてきているせいか、大気がからりと乾いている感じで、比較的快適に日中を過ごすことが出来る。
今年の夏の暑さは、かなり異常なものだった。
これが当たり前になるようであれば、夏の間の身体的負担はそうとう大きなものになりそうだと、つい思ってしまう。
現在、少々夏ばて気味なのかもしれない。
暑さそのものは、もともとは嫌いではなかったはずなのだが、さすがに体力的につらいところが現れてきているのかもしれない。
俳句関係のお仕事は、なんとか講評をすべて書き終え、推敲段階に移ることが出来た。
総評は、近日中に書き終えなければならない。
結社誌に送るエッセイも、とりあえずは先ほど書き終えた。
今月中が締切なので、こちらも推敲の段階に移る。
それらが終われば、10月末の小さな講演会の準備に向けて、一月半ほどそちらの方に力を入れなければならない。
昨日のNHKの番組で、なぜ日本は第二次大戦末期に無差別空爆を受けることになったのかを、アメリカの資料をもとにかなり丹念に報道していた。
戦争を計画立案し、遂行する者達のある種の異常さとか、その挙げ句に、いわば悪魔に魂を売り払うような非人間的な局面などを見せつけられたような、嫌な思いになった。
当事者達は、一人として戦場で死ぬことはなく、戦後は英雄として相当の社会的地位を与えられ、孫と釣りに興じる的な安穏な生活を送っていたりする。
彼らの中の、個人と国家とのありようの乖離の巨大さと空疎さに、冷え冷えとした思いを感じた。
過去の話でも、他人事でもないことだろう。
【17年8月25日】
京都へ向かう中国道は、中国山地を縦断し、横断しているのだが、その山陽側に入った辺りから、高速道に面した山の斜面のその裾あたりに、百合の花の群落が道沿いに何カ所も眺められる。
白いヤマユリなのだろうが、お盆も過ぎたこの時期にずいぶん沢山咲いていて、京都へ向かう道中の目の慰めになったりした。
昨日早朝、涼しいうちにと近所を歩いていると、道路の側溝の鉄蓋の隙間に、百合の花が1本咲いているのを見つけた。
それが、写真の花なのだが、よくこんな所に咲いているものと、感心した。

おそらく鉄の仕切の間に、わずかばかり溜まっていた土に根を下ろしてそのまま花をつけたのだろうけれど、植物のたくましさというものをつくづく感じた。
ここはちょうど民家の門の真ん前でもあり、その家の人がおそらく抜いたりすることもなく、そっとそのままにしておいたのだろうと思われた。
年に一度の選句・講評のお仕事が、今年も送られてきた。
ここ3日ほど、午前中の時間をそのために使っている。
ざっくりとした選は一日で終わったけれど、昨年に比べて、成人の部に良い作品がたくさんあって、その後入選作を絞り込むのに苦労した。
少年の部は、こちらも良い作品が多くて、楽しく選ができた。
講評と総評を両部門について、書き進めているけれど、8月中には書き終えそうだ。
【17年8月22日】
日・月と京都行き。
俳句講座の4日目のお手伝いに。
と言いつつ、京都行きはかなり大きな気分転換の機会でもある。
日曜日は、フリーなので、夕方から知人と浅酌。
夜の四条大橋から祇園界隈を、ちょっと酔っぱらいながら逍遙する。
観光客が多い。特に、外国からの家族連れの観光客が、本当に多いと思う。
月曜日は、龍大での俳句講座。
若干欠席者が増えたけれど、120人くらいは受講生がこの最終日も参加した。
3つの連続講座。
受講態度は、結構良いように思う。
講座への食いつきも悪くはないような気がする。
そんなこんなで、夏期講座4日間は終了する。
今年の夏も、これでおしまいという感慨がちょっとある。
バスの時間の関係で早めに失礼する。
京都駅の、いつもの中華料理店で夕定食を食べて、高速バスに。
朝が、4時過ぎには目が覚めていたので、その分席に着くと眠くなる。
4時間強の行程も、うつらうつらの時間が挟まっている分、早く過ぎたような気がする。
月曜日。
読書と、モニターレポート書きと、犬の病院行きとで、一日終わる。
昼過ぎには、大雷雨襲来。ひどい雨と雷だった。
その後、蒸し暑くて、昼間ではあったけれど、エアコンを使う。

おまけの、茸の写真。
これも、過日の「歩き」で見かけたもの。「オニフスベ」なのだろうか。
ジブリアニメの『もののけ姫』の中の森の精みたいな姿をしているように思う。
【17年8月16日】
ふり返ってみれば、安全保障法案の通過で、一部集団的自衛権は容認されたことが、今回のごたごたの日本側の事情だ。
個別的自衛権のみを認めていた従来の憲法に従って、日本はベトナム戦争に参戦することを免れた。
集団自衛権の容認により、もともと米国と北朝鮮の政治的問題であったミサイル問題が、集団的自衛権の規定する範囲に含まれるらしい、ということで、日本自体がこの問題の当事者の一人的な立場を否応なく背負わされることになってしまったらしい。
国民の中でも、安保法案を了解し了承した人たちが、今現在においてもどの程度であるのか、よくは知らない。
ましてや、日本が戦場となり、自分たちが戦死者の一人になるかもしれないということを本気で覚悟している人たちがどれほどいるのか、私にはわからない。
それどころか、おそらく多くの人たちは、まるで貰い火事のように、米朝2国間の紛争に日本が巻き込まれているということを、どの程度自覚しているのか、おぼつかないところがあるのではないか。
安全保障法案といいながら、実は日本がアメリカ発の戦争に巻きこまれる、そんな危険性をはらんだまさに「戦争」法案であったことが、露骨に現実のものとして、今回明らかになったような気がする。
今にして思えば、総理が「国民の命と財産を守る」と高らかに言上げした背景には、その過程で生じる「戦争に我が国が勝利する」ということが条件として隠されていたのかもしれない、と思う。
そして、ついでにいえば、恐らく政治家や企業人の中には、様々な利害得失の中で本気で日本が戦争に参加することを望んでいる人たちがいるらしい。
その神経や感覚が、私には良くは理解できないのだけれど、一般の国民の中にも、同様の傾向を持つ人たちがいるようだ……。
そんな連中が、他人を非国民と決めつけ、あたかも国家から自身に権威を付与されたかのように思いこんで、威張り散らしたりすることにもなるのかもしれない。
漫画みたいだけれども。
想像力の枯渇が恐ろしい。
【17年8月15日】

歩いていて見つけた茸。
傘の径が15センチくらいもあった。
どうやら「オオシロカラカサタケ」というものらしい。
本当に、名前通りの茸だと思う。
漢字に置き直したら「大白唐傘茸」という風なことになるのだろうか。
歩いていると、いろいろ目につくものがあって、なかなか面白い。
今日は母の運転手で病院へ。
午後早い時間帯で、検査はほんの30分ほどですべて終了したけれど、その後の診断で延々3時間ほど待ちがかかる。
夕方になって、やっと終了。
すでに待合室には人の姿はなかった。
指定時間に受診にいったのだけれど、ここまで時間がかかるとは、と二人ともにかなり疲労を感じる。
当日診察申し込みの人は、おそらくその倍くらい待ち時間があったことだろう。
目の疲れがひどくて、読書にまでもろに影響が出る。
今年の春先くらいから、細かい文字が読みづらいなと思っていたら、みるみる読めなくなった。
特に、古文・漢文関係は文字が小さく、注釈文はさらに細かい文字で、本当に困惑気味。
仕方なく、目薬を使うことにした。
どの程度、効果があるのだろうか。
メガネを変える必要があるかもしれない。
なんとも鬱陶しい。
とはいえ、『増鏡』読了する。
最後の方は、歴史物らしい迫力で、大変面白かった。
【17年8月15日】

昨夜来の雨が、朝の時間帯だけ止んだ。
数日怠っていた「歩き」に出かける。
曇天のおかげで、気温はさほど高くない。
幾つかの歩きのコースのうち、農業用水路沿いの道をあるいていると、舗道に平行する植栽のその葉の上に、しろっぽいものが乗っかっていることに気付いた。
顔を寄せてみると、それがカマキリの脱皮後の皮(蛇なら「蛇の衣」、蝉なら「うつせみ」とかいうのだろうけれど)だった。
カマキリ本体を見ることは、珍しくないけれど、脱皮後の皮を見たのは生まれて初めてだったので、さっそく携帯のカメラにおさめた。
雨滴を残した葉の上に、妙に乾いた様子で残っているカマキリの姿をきちんと残す皮は、ずいぶん印象的だった。
もっとも、昆虫の苦手な人なら、きゃっと叫んで逃げ出すのかもしれないけれど。
京都での俳句講座の際、これは例年のことなのだが、蝉の殻「うつせみ」を気味悪がって、敬遠する男子学生が大半で、その都度講師間の話題になったりしたものだ(これもセクハラ的発言になるのかもしれないけれど)。
ウルトラマンのバルタン星人のモデルだったりもするのだが、やはりその外見をグロテスクに感じたりするのだろう。
そういえば、「ウルトラQ」で怪獣ガラモンを操縦する悪玉宇宙人もまた、「うつせみ」あるいは蝉をモデルにしていなかったか、などとも思う。
今日は、半日かけて、結社誌に載せる読書ガイドを書き終える。
できれば、今後も関西に関係があるような書物を中心に書ければよいな、と思う。
今月末には、同じく結社誌に載せるはずの故郷の季語関係の文章を準備しなければならない。
ネタを考えるのが、一苦労ではある。
連日、北朝鮮のミサイル問題が報ぜられてある。
マスコミも過熱気味にあちらでもこちらでも報道し、中にはグアムまでレポーターを派遣して、現地の様子を伝えたりもしている。
それにしても、当地にこのお盆期間中にどれくらい日本人がバカンスに出かけて行ったことだろうか、などと思ってみたりもする。
トランプは、今回の騒動で支持率を上げたらしい。
安倍総理も「国民の命と財産を守る」と神妙な表情で、インタビューに答えたりしている(そのわりには、地元の盆踊りに妻同伴で参加したりもしているらしいけれど)。
低迷する支持率の起爆剤に、という思惑がそこにないはずはなかろう、などとも思う。
総じて、政治的茶番劇のような印象を持つ。
とはいえ、もし仮に北朝鮮がグアム本島に本気でミサイルを撃ち込んだら(そうではなく、正当な手続きを踏んで、周辺地域を指定してミサイル発射実験を実施した場合は、問題にはないらしいけれど)、この茶番すら一挙に吹っ飛ばす事態になることだろうけれども……。
【17年8月12日】

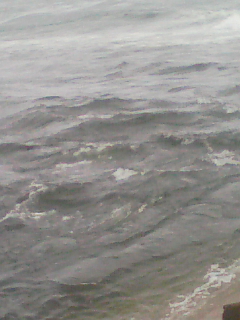
昨日、午後遅く京都から帰宅。
帰省ラッシュのピーク の日ということだったけれど、高速バスは1時間余りの遅延で到着。
宝塚を抜けるまでに時間がかかり、さらに中国道の山中でも渋滞に巻き込まれる。
中国道は、事故も工事もないのに何故渋滞が、と思ったけれど、通過してみると、長い上り坂の後、急カーブの下り、さらに複数の長いトンネルという渋滞3条件がすべてそろったようなところで、長い渋滞も納得する。
帰宅後、甥の送り迎えで少し時間があったので、久しぶりにH川の河口まで出かけて見る。
H川は、西部地区最大の河川で、中国山地奥深くを源流とする川だ。
最後は日本海にそそぐのだが、その河口が川の流れと日本海の波の作用で、小さな砂嘴のようになり、写真の手前の1カ所から川水が海に流れ込んでいる。
川の側は砂嘴に流れを妨げられて大きなプールのようになっていて、季節になると水上バイクが川面を走りまわっていたりもする。
今日も、数グループが来ていたけれども、時間が遅かったせいか、運転の様子など眺めることは出来なかった。
本日は、結構波が高くて、県内の海水浴場では水難事故も起こったらしいが、河口ではその水流と波とがちょうどぶつかり合うような状態になっていた。
大きな波と水流とが打ち消しあって、細かい波の動きに変わっていた。
ここは、春先には氷魚汲みが行われたりする場所でもある。
堤防の上から、しばらくの間、川と海とのせめぎ合いの様子を眺めていた。
京都の1週間は、終わってみればまさに「あっという間」の印象だった。
環境が大きく変わり、変化のある楽しい毎日だった。
田舎暮らしの身には、人の数の多さだけでも結構様々な刺激になる。
ウイークリーマンションの窓から見上げるビル群やその向こうの京都タワーなども、1年に一度の風景ということで、なかなか見応えがある。
月がきれいに出ている時の、ライトアップされた京都タワーとの情景は、都市的な風情を感じたりもする。
俳句講座は、150人くらいの参加で、楽しいものだった。
二日目の宇治吟行も、台風後のダム放水の影響で、塔ノ島に渡ることが出来ず、鵜小屋の見学などが出来なかったのは残念だったけれど、増水の宇治川の迫力を堪能することができた。
増水時を狙っての鮎の掛け釣りというのも、間近に見学することができた。
天気はよかったけれど、風もあり、思ったほどには過酷な吟行とならなかったのも助かった。
例年食べる宇治抹茶ソフトを、今年は食べ損なったのが心残りではあるが……。
受講生諸君は、吟行と2度の句会を経験した。
この体験を通じて、俳句に興味を持ってくれたら幸いである。
俳句講座は、21日に最終講が開かれる。
【17年8月4日】
今日は、たいへん暑かった。
とはいえ、気温は35度どまりではあったけれど。
しかし、その気温が夕方になってもほとんど下がらないという状態だった。
隣の町は下がり止まり状態だったけれど、我が町の方はいったん少し下がった気温が夕方に向けてまた上がり始めるという変則的な気温変化だった。
もちろん、終日ほぼ晴天という状態の下でのことだったので、一体どういうことなのかと思った。
これも、遠く沖縄近辺にある台風5号の影響のひとつなのだろうか。
雲の変化が多彩である。
明日から、しばらく京都行き。
今日は、その準備に終日使う。
とはいえ、短期のマンションで宿泊ということで、生活に必要な調度類はそこに概ね用意されてあるのだけれど。
龍大の俳句講座にあわせて、この時期にマンションを借り始めて3度目の夏ということになるのだが、トランク一つの荷物で、その期間を過ごすことができるのはありがたい。
ネット環境もそれなりに整っているので、ブログの書き込みなどはできないわけではない。
十月には、岩城先生についての講演会を持つことになっているので、その準備を始めるきっかけにしようとも思う。
あいにく、その時期に合わせるように、台風が九州から西日本、さらには近畿地方辺りを通過しそうなので、講座の開講に影響がでないことを願うばかりである。
二日目の宇治吟行も、荒天のもとということになれば、ほぼ中止ということになりそうだ。
それにしても、日没後であるにもかかわらず、暑い。
【17年8月2日】
2泊3日の京都泊まりは、楽しかった。
初日の丹後「すき句会」は、すでに会を始めてから13年が過ぎようとしているらしい。
長い句会だったけれど、今後どうなっていくかははっきりとはわからない。
とはいえ、おそらくこの「すき句会」は、いわゆる句会というよりは、短歌の歌会に近いような性格をもったところがあるのかもしれない、とは思う。
俳句とはなにか、という基本的な問題意識を持ちながら進められる句会というのは、意外と少ないのではないかと思われるからだ。
「すき句会」はそんな句会のひとつである。
それも、主宰の岩城先生の姿勢というものが大きく関わって来ている結果と思う。
なかなか面白い句会であると思う。
二日目の「醍醐会」は、長谷川櫂氏と坪内稔典氏を話題にした研究会。
特に、長谷川氏のレポート担当の方の「憑依」という考え方から長谷川氏の作品を捉え直そうという提言は、色々な意味で強烈で刺激的であった。
こうでなければ、「醍醐会」じゃない、というようなテンションの高さのまま二次会に進み、おおいに談論風発状態となる。
面白い。
2連泊したのは、祇園花見小路に近いカプセルホテルで、安くて、割と清潔で、サウナ付きの風呂にも夜でも朝でも自由に入ることが出来て、ちゃんとそれなりに美味しい朝食バイキングが付いていてということで、大変お気に入りの宿だった。
8月にもすでに1泊2日の予約を済ませている。
きっと10月にも今回同様、2泊3日でここに泊まるだろうな、と思う。
田舎暮らしに何の不満もないけれど、たまには都会(京都は本当の意味での都会という印象からは外れてはいるけれども)的な雰囲気を味わうのも悪くはない。
一望、数十人から数百人の人の姿が目に入るなどということは、地元ではほぼないことなので、それだけでも刺激的ではある。
水曜日。壊れていたエアコンの修理の方が来られる。
ほとんど使っていなかったにもかかわらず、勝手に故障したという印象が強いのだけれど、修理自体は大がかりなものとなった。
人間の手術でいえば、ほぼ臓器移植手術のようなもので、冷却機構の部分と、本体背面カバーの部分を総替えした。
修理担当の若い人がやってきて、冷房のない部屋でほぼ2時間半の作業だった。
さすがに気の毒で、冷蔵庫にあったポカリスエットを進呈した。
素人目には、ものすごく複雑な修理作業であったが、見事に修復。
夕方、試運転を兼ねてしばらくエアコンを動かす。
大丈夫そうである。
7月の異常な暑さが、昨日今日と、夕方にはおさまっているようだ。
日が沈むと、涼しい風が吹き始める。
大変心地よい。